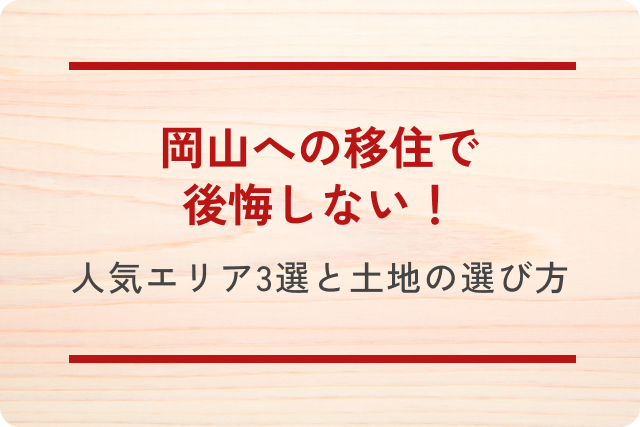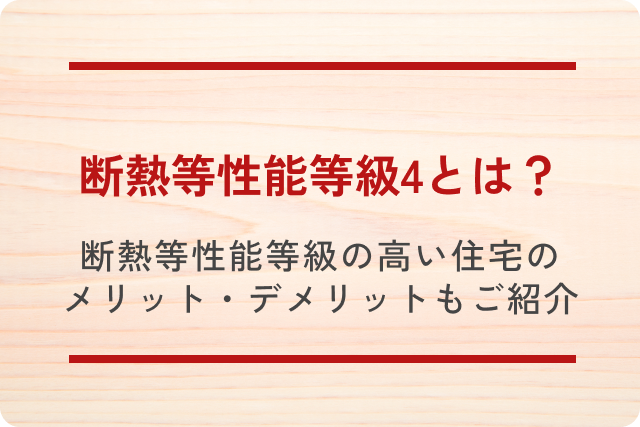
断熱等性能等級4とは?断熱等性能等級の高い住宅のメリット・デメリットもご紹介!
これから家を建てる人にとって、住宅の断熱性能は重要なポイント。しかし「断熱等級」と言われても、具体的にどんなメリット・デメリットがあるのか分かりにくいものです。
そこで 本記事では、「断熱等級4」の住宅の特徴や、等級5との違い、メリット・デメリットを分かりやすく解説します。さらに、断熱性能を知るためのUA値やηAC値についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
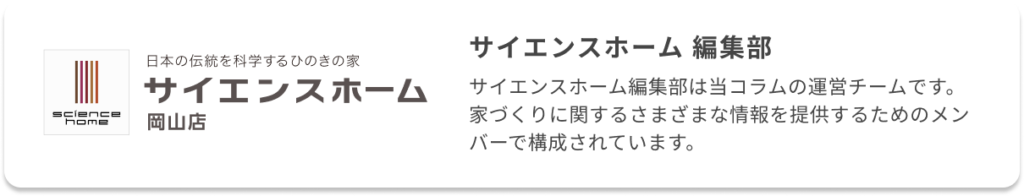
断熱等性能等級の基本情報
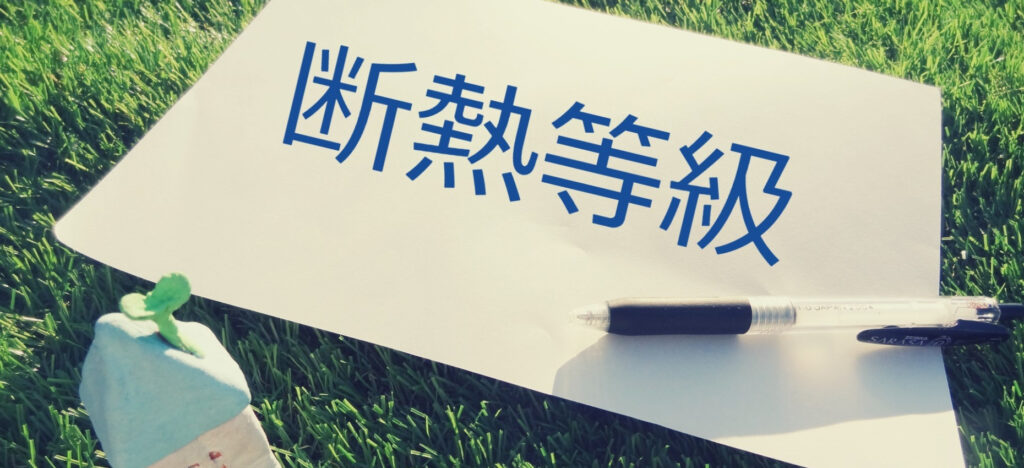
住宅の断熱性能を評価する指標の一つに「断熱等性能等級」があります。これは、国の住宅性能表示制度に基づく基準で、住宅の断熱性能を1から7までの等級で評価するためのものです。
数値が大きいほど断熱性能が高く、省エネ効果も向上します。この等級は、屋根や壁、床、窓といった建物の外皮の断熱性を考慮して決定されます。また、日本の気候は地域によって異なるため、全国を8つの気候区分に分け、それぞれに適した基準が設けられています。
参考:住宅性能表示制度における省エネ性能に係る上位等級の創設
住宅性能表示制度
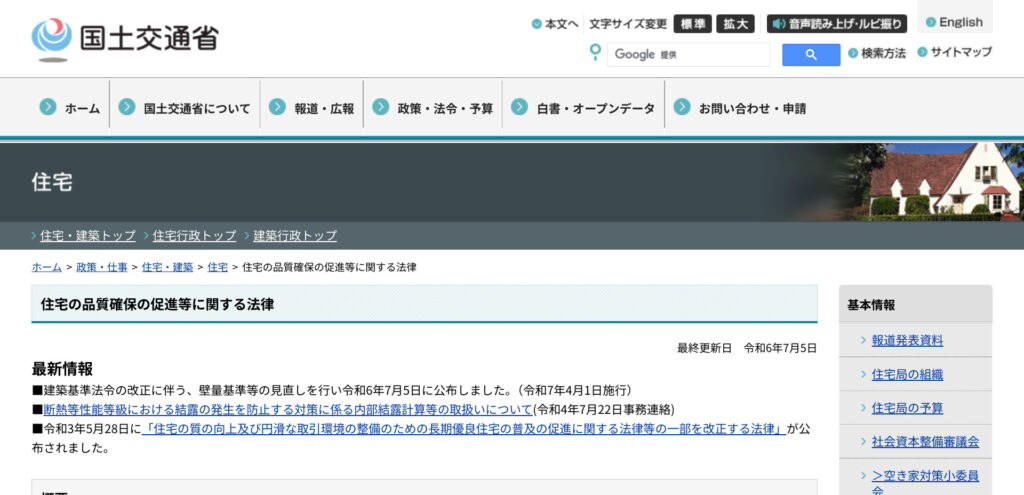
住宅の品質は、専門知識がないと判断が難しいものです。そこで、国土交通省は「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき、住宅性能表示制度を導入しました。
この制度では、第三者機関が住宅の性能を客観的に評価し、消費者が安心して住宅を選べるようになっています。評価項目は10種類あり、中でも「構造の安定」「劣化の軽減」「維持管理・更新への配慮」「温熱環境」の4つが特に重要視されています。
断熱性能もこの制度の重要な要素であり、快適な住環境を維持するために欠かせない指標の一つとされています。
断熱等性能等級4とは?

断熱等性能等級4は、かつて住宅の断熱性能における最上位の基準とされていましたが、2022年以降、より高い等級が新設されました。
それでもなお、等級4は高い断熱性能を持つ住宅の基準とされ、長期優良住宅の認定基準の一つにもなっています。この等級では、建物の外皮性能として「H25年省エネ基準」の基準値を満たすことが求められ、地域ごとにUa値やηAC値の具体的な基準が定められています。
2025年4月からは、新築住宅に対してこの基準の適合が義務化される予定であり、省エネ住宅の標準となる見込みです。
参考:省エネ基準適合義務化
2022年4月以降に等級5以上が新設
2022年4月に断熱等性能等級5が新たに導入され、これまで最上位だった等級4は最低限の基準となりました。2025年からは等級4以上の断熱性能が求められ、等級3以下の住宅は新築できなくなります。
この変更は、より快適で省エネ性能の高い住宅の普及を促進するために行われたものです。さらに、同年10月には戸建住宅向けに等級6・7が追加され、より高性能な断熱基準が設定されました。
加えて、経済産業省は2030年までにZEHの普及を目指しており、今後も住宅の省エネ基準は厳格化していくと考えられます。
参考:建築物省エネ法関係
等級4と等級5の違い
断熱等性能等級5は「ZEH(ゼッチ)」と同等の断熱性能を持つ基準として設けられました。さらに、高い断熱基準として「HEAT20」が存在し、より優れた省エネ性能を実現できます。
等級4と比較すると、等級5は使用される断熱材の厚みが増し、特に天井や壁では約1.2倍の厚さが求められます。これにより、室内の温熱環境が向上し、冷暖房の効率も高まります。今後、新築住宅を検討する際には、等級4以上の高い断熱性能を確保することが重要となるでしょう。
断熱性能を確認する方法

住宅の断熱性能を正しく理解するためには、UA値のほかにC値(住宅の隙間の量を示す指標)やQ値(熱の逃げやすさを示す指標)にも注目することが重要です。これらの数値を把握することで、より適切な住宅選びが可能になります。
また、建築士には省エネ性能について説明する義務があるため、不明点があれば詳しく聞くことができます。さらに、第三者機関に依頼して図面調査や現地調査を行い、断熱性能を確認する方法もあります。ただし、施工後の改善には限界があるため、計画段階で慎重に検討することが大切です。
関連記事:高気密高断熱の住宅とは?メリット・デメリットや施工方法の種類を詳しくご紹介します!
断熱等性能等級の高い住宅のメリット・デメリット

断熱等性能が高い住宅には、メリットだけでなくデメリットも存在します。これから家を建てる方は、両方を理解した上で検討を進めることが大切です。
メリット
今後、断熱性能の基準が強化されることで、建築コストや工期に影響を与える可能性があります。しかし、これにより住宅の快適性や資産価値が向上するという大きな利点もあります。
断熱性の高い住宅は、夏は涼しく冬は暖かいため、居住環境が快適になり、冷暖房の使用を抑えることで光熱費の削減にもつながるでしょう。さらに、省エネ住宅向けの住宅ローンの優遇措置や、自治体の補助金を活用できるケースもあり、経済的なメリットも期待できます。
デメリット
断熱性能を向上させるには高性能な断熱材の使用や単板ガラスから複層ガラスへの変更、インナーサッシの導入などが求められます。これにより建築コストが上昇する点は考慮すべきポイントです。
一般的に、断熱等級4から5に向上させるには約10万円、等級6では約60万円、等級7となると250~300万円の追加費用がかかるといわれています。ただし、これらの費用は目安であり、住宅の規模、地域区分、防火地域の指定の有無、使用する断熱材や窓・サッシの種類によって大きく変動する可能性があります。
サイエンスホーム岡山店が選ばれる3つの理由
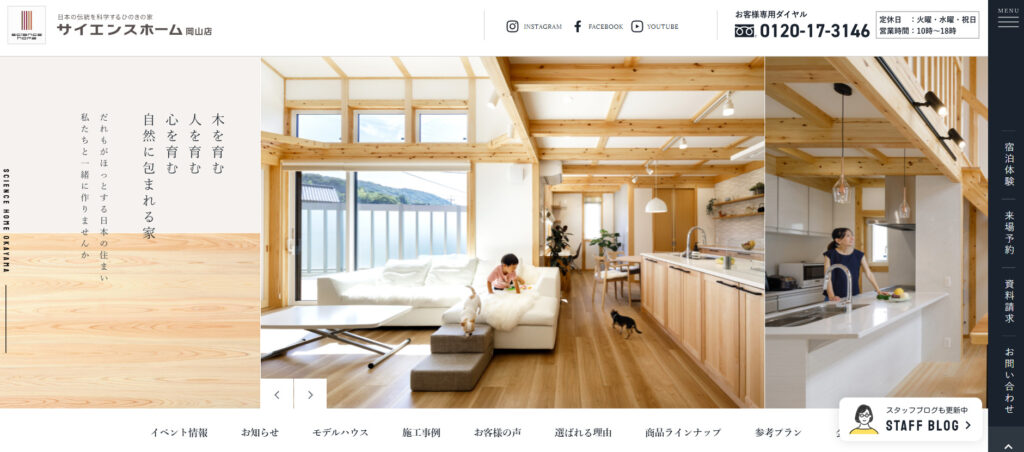
次に、サイエンスホーム岡山店が選ばれる理由について解説します。
・ひのきの家
・真壁づくり
・性能と品質
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.ひのきの家
ひのきは古来より「木の王様」と称され、香りや触り心地が人に安らぎを与えています。このため、森林浴を思わせるようなひのきの家では、五感育ちの自然の癒しを実感できます。ひのきで作られた家に住むと、日々の生活のなかで木が持つ温もりを感じられやすいです。
サイエンスホームのひのきの家は、無垢の国産ひのきを贅沢に使っています。素材の美しさを保ちつつ、触れられる楽しさや香りに包まれる心地よさを追求しています。ストレスフルな現代において、ひのきの家は心の癒し、暮らしを豊かにする選択肢の1つです。
2.真壁づくり
「真壁づくり」は、日本の伝統的な建築工法を現代に伝えた住まいづくりが特徴です。柱や梁などの構造材を室内に見せるため、木の温もりを視覚や触覚で楽しめます。さらに、木が呼吸する特性によって、室内は快適な湿度が保たれ、空気環境も心地よいものになります。
また、サイエンスホームが提案する「真壁づくりの家」は、2015年にグッドデザイン賞を受賞しました。 木の質感や吸湿性を最大限に活かしながら、施工の効率化と価格の手頃さを両立した点が高く評価されています。
3.性能と品質
サイエンスホームが提供する住まいは、一年中快適な暮らしを支える外張り断熱であるため、高気密・高断熱仕様で、季節問わず快適に過ごせます。また、軸組とパネルを組み合わせたハイブリッド工法は、耐久性と安定性のある強固な構造が可能です。
また、内部建具や床には無垢材を使用しており、人と環境に優しいだけでなく、自然素材ならではの触り心地や温かみを感じられます。さらに、吹き抜けは、明るさと開放的な室内をもたらすため、居心地の良い空間を作り上げます。
なお「サイエンスホーム岡山店」は、ひのきの家や真壁づくりといった日本の伝統的な技法と、現代の高気密・高断熱技術を融合させた家づくりが特徴です。家づくりをご検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。⇒サイエンスホーム岡山店への相談はこちら
断熱等性能等級4でよくある3つの質問

断熱等性能等級4の住宅に関して、よくある質問とその回答をまとめました。
質問1.断熱等級が高い家を建てる際のポイントは?
高断熱の住宅を建てる際は、いくつかの重要なポイントがあります。まず、気密性が高まることで湿気がこもりやすくなるため、適切な通風計画を検討することが不可欠です。自然の風を活用するために、屋根裏や基礎部分の換気を工夫し、部屋の配置や窓の開閉方式を考慮することが大切です。
次に、窓の配置と種類も重要です。断熱性能を高めるには、窓の数を減らしたり、熱の出入りが少ない構造にすることで室温管理がしやすくなります。また、施工の精度が断熱性能に大きく影響するため、経験豊富な建築会社に相談することも重要です。
質問2.断熱性能を表すUA値・ηAC値とは?
建物の断熱性能を評価する際には「熱がどれだけ外に逃げるか」と「日射熱がどれだけ室内に入り込むか」の2つの指標が用いられます。
前者は外皮平均熱貫流率(UA値)で表され、数値が低いほど建物の断熱性能が高いことを示します。UA値は、屋根や壁、床、窓などから逃げる熱の総量を外皮全体の面積で割ったものです。
一方、後者は冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)と呼ばれ、建物に入る日射熱の割合を示します。この値も小さいほど、夏場の室内温度上昇を抑えやすくなります。
質問3.断熱工法の種類とは?
断熱工法には、主に「充填断熱」「外張断熱」「付加断熱」の3種類があります。充填断熱は、壁や天井の内部に断熱材を埋め込む方法で、グラスウールや吹き付けウレタンなどが使われ、古くから普及している工法です。
外張断熱は、ウレタンフォームやポリスチレンフォームなどの断熱材を建物の外側に施工する方法で、施工コストは高くなるものの、断熱性能に優れています。付加断熱は、充填断熱と外張断熱を組み合わせた工法で、高断熱性能を求められる寒冷地やZEH住宅で採用されるケースが増えています。
まとめ

断熱等性能等級4は、2022年4月以降の等級5以上の新設以前は高水準の断熱性能を示すものでした。省エネ性、快適性、健康面でのメリットがある一方、初期費用はやや高くなる傾向があります。
UA値やηAC値、断熱工法の種類など、住宅性能を理解することで、より良い家づくりが可能になります。なお「サイエンスホーム岡山店」は、ひのきの家や真壁づくりといった日本の伝統的な技法と、現代の高気密・高断熱技術を融合させた家づくりが特徴です。
家づくりをご検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。⇒サイエンスホーム岡山店への相談はこちら
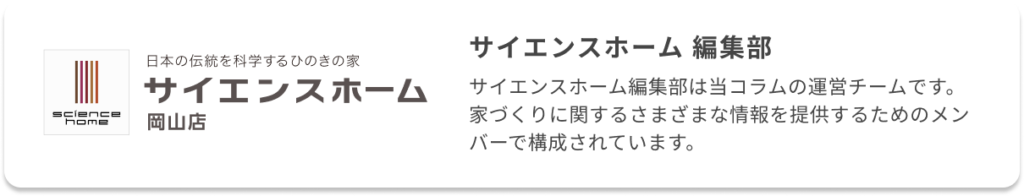
-

2026年完成見学会2月21日~23日予告
2026年初の完成見学会が岡山市南区箕島で2月21日~23日の3日間平屋大屋根の完成見学会を行いますので、詳細は後日お知らせします。お楽しみに!
-
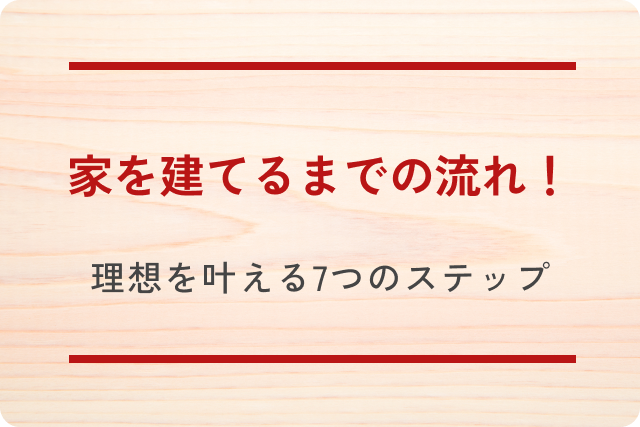
家を建てるまでの流れ!理想を叶える7つのステップ
夢のマイホームに向けて一歩踏み出したものの、家を建てるまでの流れが複雑で、何から始めればよいか不安を感じている方は少なくありません。後悔のない住まいを実現するには、各工程の目的を正しく理解する必要...
-
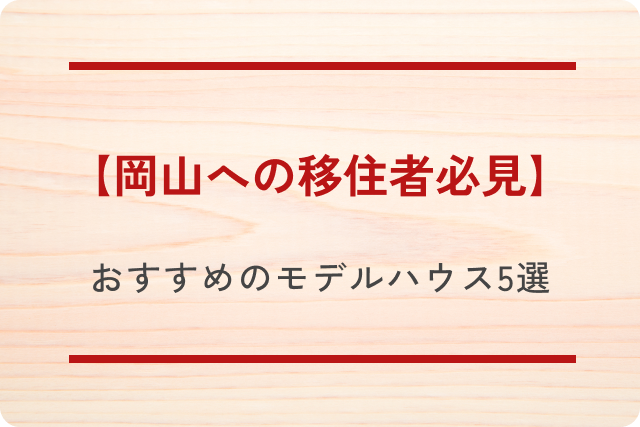
【岡山への移住者必見】おすすめのモデルハウス5選
岡山への移住を検討している方で、「岡山にはたくさんの住宅メーカーがあって、どこを見に行けばいいのか分からない」「土地勘がない中で、自分たちに合ったメーカーをどう選べばいいの?」というお悩みをお持ち...