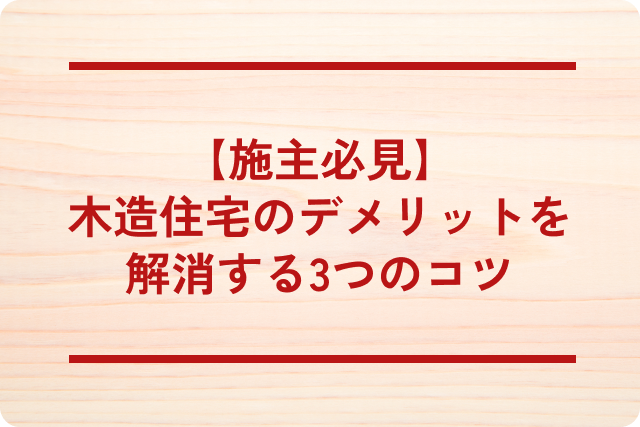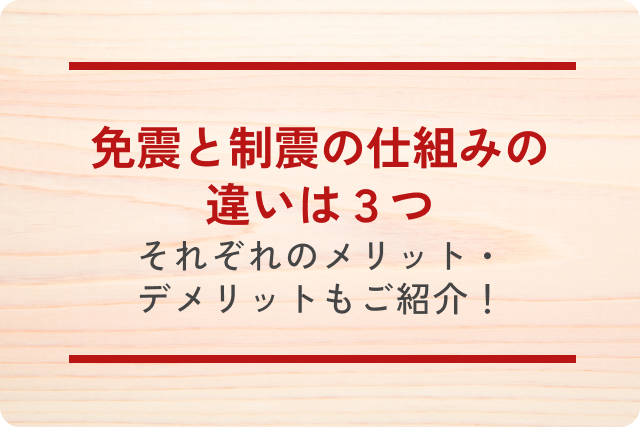
免震と制震の仕組みの違いは3つ|それぞれのメリット・デメリットもご紹介!
地震大国である日本において、住宅の地震対策は家づくりを検討する際には欠かせない要素です。建物の安全性を高める構造として「免震」や「制震」という言葉を耳にする機会は多いものの、両者の違いを正確に理解できていない方もおられるのではないでしょうか。
本記事では、免震と制震の違いについて、仕組みやメリット・デメリットを分かりやすく解説します。ご自身の家づくりに最適な地震対策に取り組んでください。
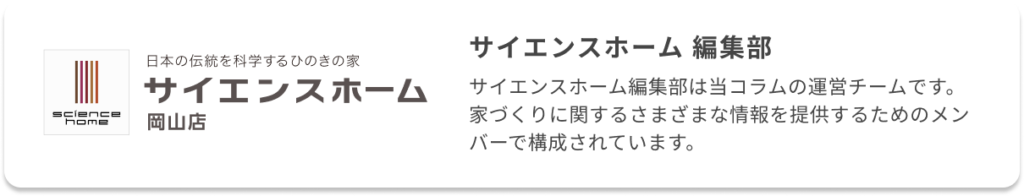
免震と制震の仕組みの違いは3つ

免震と制震は、どちらも建物の揺れを抑えるための構造ですが、その仕組みには大きな違いがあります。ここでは、免震と制震の仕組みを分かりやすく比較するため、それぞれの考え方や特徴について解説します。
1.揺れへの対処方法
免震構造は、建物と地盤を切り離すと、地震の揺れを建物に直接伝えないようにします。一方、制震構造は、建物に設置された装置で揺れのエネルギーを吸収して、揺れ幅を小さくする点が特徴です。
免震は、地面が大きく揺れても建物自体はゆっくりと揺れるため、建物内部への衝撃を大幅に軽減できます。一方、制震は、建物の揺れは発生するものの、その揺れを効率的に抑えることで建物へのダメージを減らします。
2.構造材と装置の種類
免震構造では、建物の基礎と建物の間に、地震の揺れを吸収したり減衰させたりするための特殊な装置を設置します。主な装置として、建物を支えつつ水平方向に変形することで揺れを逃がす積層ゴムや、揺れのエネルギーを熱に変えて吸収するダンパーなどがあります。
これらの装置が協調して働くと、地震の揺れが建物に伝わりにくくする仕組みです。一方、制震構造では、建物の柱や梁、壁などの内部に制震ダンパーを設置します。
このダンパーが地震による建物の変形を利用して、揺れのエネルギーを吸収したり減衰させたりします。制震ダンパーの素材は、オイル、ゴム、鋼材など、さまざまです。
3.効果と適した建物の違い
免震は、地震の揺れを建物に伝えにくくするため、建物全体の揺れを大幅に軽減する効果があります。特に高層ビルや病院など、建物内部の精密機器や家具の転倒の防止を求められる建物に適しています。
しかし、建物と地盤を切り離す構造のため、広い敷地が必要になったり、コストが高くなったりするデメリットがあります。一方、制震は、揺れのエネルギーを吸収すれば、建物の損傷を軽減する効果があります。
特に、高層の建物や、耐震性能が高い建物に制震を組み合わせると、繰り返しの地震や風による揺れにも強くなるでしょう。免震に比べてコストが抑えられ、比較的狭い敷地でも設置が可能です。
そのため、一般の戸建て住宅にも広く採用されています。
免震と制震のメリット・デメリット

免震と制震は、それぞれに独自のメリットとデメリットがあります。家づくりにおいてどちらを選択すべきか判断するためには、コストやメンテナンス性、他の構造との組み合わせなど、複数の視点から比較しましょう。
1.コストと工期
免震と制震は、採用する際のコストと工期に大きな違いがあります。免震構造は、基礎部分に特殊な装置を設置する必要があるため、制震構造よりも初期コストが大幅に高くなる傾向があります。
また、免震装置の設置や建物の構造計算に時間がかかるため、工期も長くなる場合があるでしょう。一方、制震構造は、建物の内部にダンパーを組み込むため、免震に比べて初期コストを抑えられます。
また、工期も比較的短く済む場合が多く、家づくり全体における負担を軽減しやすいといえます。コストと工期のバランスを考慮すると、一般的な戸建て住宅では制震構造が選択されやすい傾向があるでしょう。
2.メンテナンスと耐用年数
免震装置には、積層ゴムなどの部材が含まれるため、定期的な点検や将来的な交換が必要になる場合があります。特に、免震装置が設置される地下部分は、点検が容易ではないため、メンテナンス費用がかさむ可能性があるでしょう。
一方、制震ダンパーは、建物の内部に組み込まれるため、一般的にはメンテナンスフリーとされています。ただし、大規模な地震が発生した後は、専門家による点検が推奨される場合があります。
耐用年数については、免震装置も制震ダンパーも数十年の寿命を持つとされていますが、歴史が浅い技術であるため、長期的な実証データが少ない点に留意が必要です。
3.ほかの構造との相性の比較
耐震構造は、柱や壁を強くすると地震の揺れに耐える構造であり、建築基準法で定められている最低限の基準を満たすものです。耐震に制震を組み合わせる「耐震+制震」は、建物を強くした上で、揺れのエネルギーを吸収するため、繰り返しの地震にも強くなります。
地震の揺れによる建物へのダメージが蓄積しにくくなるため、建物の寿命を延ばす効果も期待できます。一方、免震は建物と地盤を切り離す仕組みのため、耐震構造との相性を考慮した上で設計する必要があるでしょう。
多くの住宅では、コストパフォーマンスに優れた「耐震+制震」が採用されています。
関連記事:耐震等級とは?3つの等級や耐震等級が高い住宅を建てるメリットをご紹介!
地震に強い家づくりなら「サイエンスホーム岡山店」
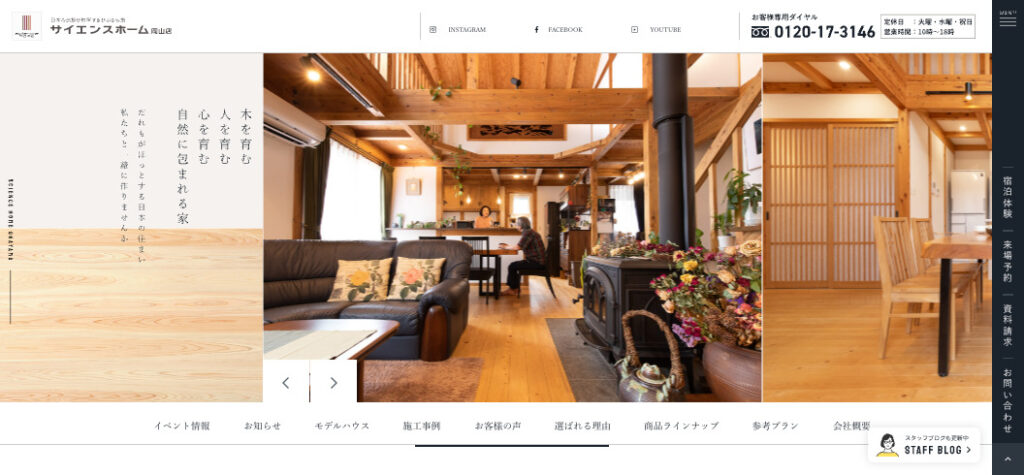
「サイエンスホーム岡山店」が提案する家づくりは、日本の伝統的な技法である「真壁づくり」と、現代の「高気密・高断熱技術」を融合させているのが特徴です。ひのきの柱や梁を室内に見せる真壁づくりは、木の温もりを五感で感じられ、心地よい湿度を保ちます。
また、一年中快適な暮らしを支える外張り断熱による高気密・高断熱仕様や、軸組とパネルを組み合わせたハイブリッド工法により、高い性能と品質を両立させています。これらの技術と伝統が融合することで、耐久性と安定性を備えた強固な構造が実現しており、安心できる住まいづくりを可能にしています。⇒サイエンスホーム岡山店への相談はこちら
免震と制震 違いでよくある3つの質問

免震と制震 違いでよくある質問をご紹介します。それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
質問1.免震と制震はどちらを選べばいいですか?
免震と制震のどちらを選ぶべきかは、建物の種類や予算、重視するポイントによって異なります。免震は、地震の揺れを建物に伝えにくくするため、家の中の家具や家電の転倒を防ぎたい場合に効果的です。
特に、高層マンションやオフィスビルなど、建物内部の安全性を最優先する場合に適しています。一方、制震は、建物の損傷を抑えたい場合に効果的です。免震に比べてコストが抑えられるため、一般的な戸建て住宅では、耐震と組み合わせれば高い耐震性能とコストパフォーマンスを両立できます。
質問2.免震構造にすると家具は倒れませんか?
免震構造は、地震の揺れを建物に直接伝えにくくするため、家具の転倒リスクを大幅に軽減する効果が期待できます。しかし、揺れがゼロになるわけではないため、家具の固定は依然として重要です。
特に、大きな揺れに対しては、建物はゆっくりと大きく揺れるときがあるため、完全に転倒を防ぐのは難しい場合があります。あくまでもリスクを軽減する対策として捉え、転倒防止策と併用することが推奨されます。
質問3.免震と制震は台風や強風にも効果がありますか?
免震は、地震の揺れに特化した構造のため、台風や強風による揺れにはあまり効果がないとされています。一方、制震ダンパーは、地震だけでなく風による揺れも吸収する効果があるため、台風の多い地域では有効な対策となります。
特に、繰り返しの風による建物の小さな揺れを吸収すれば、構造体へのダメージの蓄積を防ぐ役割も果たします。
まとめ

免震と制震は、どちらも地震に強い家づくりには欠かせない技術ですが、その仕組みや効果、メリット・デメリットは大きく異なります。免震は、基礎と建物を切り離せば揺れを建物に伝えない仕組みで、制震は、ダンパーで揺れのエネルギーを吸収する仕組みです。
初期コストやメンテナンス性、他の構造との相性などを総合的に比較すると、ご自身のライフスタイルや予算に合った最適な地震対策を見つけられるでしょう。
なお「サイエンスホーム岡山店」は軸組とパネルを組み合わせたハイブリッド工法により、高い性能と品質を両立させています。これらの技術と伝統が融合することで、耐久性と安定性を備えた強固な構造を実現しています。⇒サイエンスホーム岡山店への相談はこちら
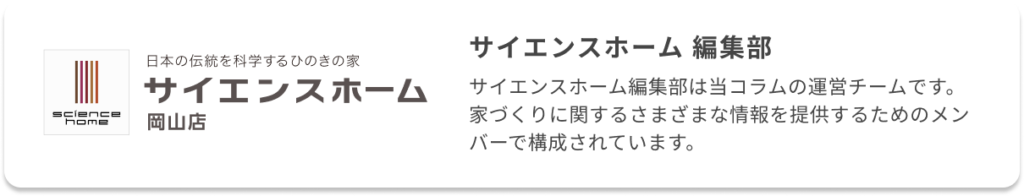
-
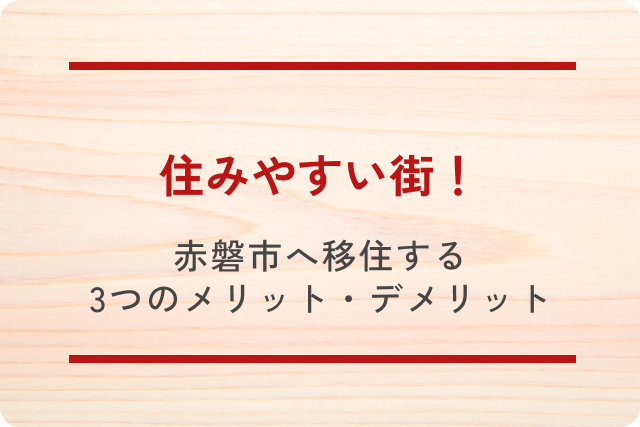
住みやすい街!赤磐市へ移住する3つのメリット・デメリット
赤磐市は、「フルーツ王国」としての豊かな食生活や、災害が少なく穏やかな気候が魅力のため、移住する場所として非常に人気です。しかし、理想の暮らしを実現するためには、地域の特性や支援制度、現地の住環境...
-
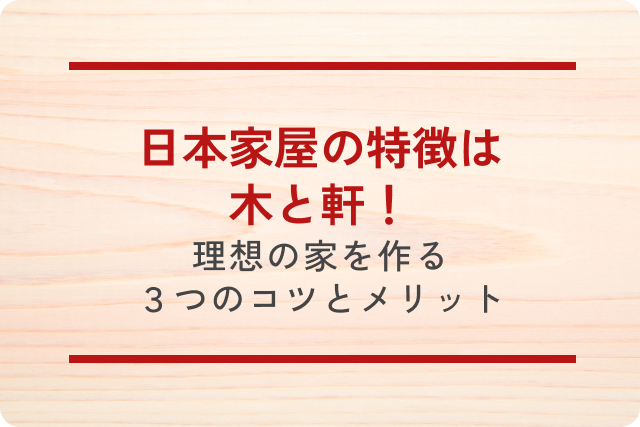
日本家屋の特徴は木と軒!理想の家を作る3つのコツとメリット
日本家屋の特徴とは、日本の風土に適応するために発展した、木材を中心とした建築様式や構造上の工夫です。「木の温もりに包まれて暮らしたい」「家族の健康を守りたい」という想いから、日本家屋の家づくりを取...
-
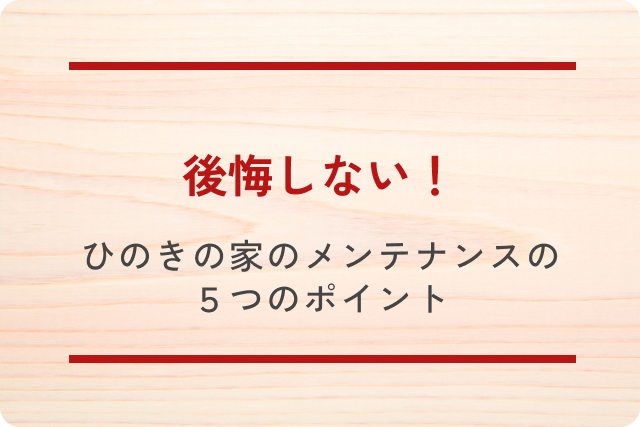
後悔しない!ひのきの家のメンテナンスの5つのポイント
ひのきの家についての知識不足や放置により、修復に多額の費用がかかる場合も少なくありません。ひのきの家のメンテナンスで後悔を避けるためには、木材が持つ調湿作用や経年変化の特性を正しく理解して、適切な...